前回書いた記事はなんと歴代の内定者の中で一番のPV数で、今では1万PVを超えております!
多くの方に読んでいただけて、本当に嬉しく思います!ありがとうございます!
今回は、4月からエンジニアとしてインターンをしていることもあり
『プログラミングの楽しさ』について、最近思うことを発信していこうと思います。
▼目次———————————————
- プログラミングと数学の問題を解くことの共通点
- プログラミングを学ぶコツ
- まとめ
1. プログラミングと数学の問題を解くことの共通点
今回のブログのタイトル通りですが
『プログラミングと数学の問題を解くことは同じだ』と僕は思っています。
ここでいう『数学の問題』は、高校の数学で
『〇〇が△△となることを証明せよ。』という問題のことです。
もともと高校のとき、僕は飽きもせず、ずーっと数学の問題をひたすら解いていました。
今、実際に仕事でプログラミングをしていますが
同じような気持ちになっており、ずーっとコードを書いていても飽きず、むしろ楽しいと思えています。
なぜ、僕は両方とも楽しめているか、その理由について考えてみました。
ポイントは3つあります。
- たどり着きたいものが決まっている
- プロセスが複数ある
- 論理的である
1. たどり着きたいものが決まっている
読んで字のごとくですが、2つともゴールが決まっています。
- プログラミング…「〇〇な処理を行いたい」「△△なアニメーションをつけたい」など。
- 数学の問題…「〇〇になることを証明せよ」と明らかですね。
2. プロセスが複数ある
『プログラミング』、『数学の問題』どちらもゴールが決まっていると上で書きました。
対して、それに向かうプロセスはどうでしょうか。
- プログラミング…『目的の動作』が満たされれば、コードの良し悪しはあれひとまず良い。
- 数学の問題…証明さえできれば、きれいかどうかはあれひとまず良い。
両方ともゴールが定まっており、そのゴールにたどり着くことができればひとまずOKでしょう。
3. 論理的である
よく言われることですが、2つとも論理的です。
- プログラミング…あらゆるコードが関連し結びついており、論理が破綻している場合、プログラムは動作してくれません。
- 数学の問題…論理が破綻していたら、そもそも証明されたことにはなりません。
2. プログラミングを学ぶコツ
『プログラミングと数学の問題を解くことは同じだ。』と思っていただけたでしょうか?
次に、『プログラミングと数学の問題を解くことは同じだ。』と思っている僕がオススメするプログラミングを学ぶコツをご紹介します。
- 文法はさっさと終わらせよう
- サンプルアプリをたくさん作ろう(永遠にこれ)
1. 文法はさっさと終わらせよう
これは、ぶっちゃけそのまんまです(笑)
数学の問題を解く際も、最低限の定義などはちゃっちゃとやるじゃないですか。
それと同じです。
2. サンプルアプリをたくさん作ろう
数学の問題もそうですが、文法(解き方)・定義がわかったところで何か解けるようになるわけじゃないですよね?
ひたすら練習問題とか章末問題とか解きましたよね?
あれと同じことです。
よく、エンジニアの人が
「自分が作りたいもの作りなよ!」
「自分が作りたいもの作りなよ!」
って言いますよね?
ぶっちゃけ
「いや、そんなもん特にねえわ!!!」
って、僕は思う派です。
自分で作りたいものがある人はそれでもいいですが、
ない人は本やサイトに載ってるサンプルなどをひたすらやっていきましょう。
サンプルアプリを作りまくっていくと、やれることが増えて自分が作りたいアプリなどが思い浮かんできます。
Androidにはなりますが、僕がオススメするAndroidの勉強方法を記事にしてみたのでもしよければご覧ください。
Android, Kotlin初心者が1ヶ月でやったことと、できるようになったこと
3. まとめ
いかがでしたか?
数学の問題を解くこととプログラミングを同じもののように捉えることができて、少しでもプログラミングを楽しく学んでもらえたらと思い書きました。
ただ、「俺はそう思わない!!!」と言うご意見もあると思いますのでお気軽に僕(@muttsu_623)までご連絡いただければと思います!
以上、19卒佐藤夢積でした。
また、次回のブログもご期待ください😊








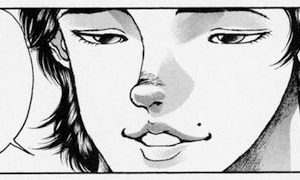












最近のコメント